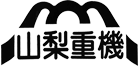
|
|
|
| スウェーデン式サウンディング試験 | |
■スウェーデン式サウンディング試験とは 荷重による貫入と回転による貫入を併用した原位置試験であり、土の静的貫入抵抗を求めるために行う。 静的貫入抵抗とは、Wsw:貫入開始後、1000N以下で貫入に必要な最低過重(N)Nsw:Wsw=1000Nの過重で貫入が止まった 後、回転により所定の目盛線まで貫入させたときの半回転数から換算した貫入量1m当たりの半回転数で表した静的貫入抵抗値(回/m)。試験は深さ10m以内の軟弱層を対象に概略調査または補足調査などに用いられる。 ■試験方法の概要 専用ロッドの先端にスクリューポイントを取り付け、調査地点に鉛直に立てる。 段階的に所定の過重(50N,150N,250N,500N,750N,1000N)し、各載荷段階の貫入量を測定する。 1000Nの過重を載荷しても貫入しないときは、ロッドを回転させ、目盛線まで貫入させるのに要する半回転数を測定する。 ■結果の利用 試験結果は、土の硬軟または絞まり具合を判定するとともに軟弱層の厚さや分布を把握するのに用いる。最近では、戸建住宅など小規模構造物の支持力特性を把握する地盤調査方法として広く普及している。 | |
| 柱状地盤改良 | |
■概 要 柱状地盤改良はセメント系固化材と水を撹拌したセメントスラリーを作成し、このスラリーを撹拌装置先端より吐出しながら回転・掘進することで、土とスラリーが固化反応し、柱状の改良体を築造することで地盤の支持力の向上と不同沈下の抑止を目的とする ■適用範囲 改良系は直径600mm以上とする。改良長は2.0m以上、8.0m以下を原則とする。ただし、2.0m未満の場合は改良径や配置および本数の検討が別途必要となる。 適用地盤は砂質土(礫質土を含む)および粘性土地盤とする。 ■設 計 柱状地盤改良設計の考え方には2種類ある。基礎下の改良体および改良体間の地盤を含めた複合地盤としての鉛直支持力を見込む設計方法と、改良体が独立して支持するとした杭的な鉛直支持力を見込む設計方法がある。 ① 柱状地盤改良の施工方法は、スラリー撹拌方式とする。 ② 改良体は、基礎立ち上りの部分に対して配置するものとし、改良体間隔は住宅基礎の剛性から2.0m程度を原則とする。 ③ 改良体の設計基準強度Fcは、500kN/m2~800kN/m2とする。 ④ セメント系固化材の配合量は原則として300kg/m3とする。ただし、配合試験で確認された場合はこの限りではない。 ⑤ 頭部処理は、基礎下端、均しコンクリート下端、砕石下端のいずれかとする。 ⑥ 支持力算出は、原則として最弱ポイントの調査データにより検討する。 ■施 工 柱状地盤改良の施工においては、設計の要求する品質を確保するため、施工計画を立て十分な混合撹拌機能を有する機械を選定する。 ① 施工準備・施工機械:柱状地盤改良の施工に支障がないように現場状況の確認や改良芯の位置確認を行う。また、施工機械や設備は、設計計画通りの施工が行える機種を選定する。 ② 地盤状況確認:柱状地盤改良は現状土と固化材を混合撹拌することにより改良杭を築造する工法であることから、現状土の影響を強く受ける。したがって、土質の確認は必須事項であり、確認された土質によっては設計変更の可能性もあるので注意が必要である。特に有機質土に関しては固化不良の原因となりやすい。 ③ 施工手順:Ⅰ位置決め、機械セット Ⅱ空堀完了 Ⅲスラリー注入混合撹拌 Ⅳ先端部定着撹拌 Ⅴ引き上げ混合撹拌 Ⅵ完了 ■撹 拌 撹拌は撹拌翼が4枚以上、共回り防止翼がついているなどの一定基準以上の形状の撹拌装置を用いて実施する。また、セメントスリラーの水セメント比(W/C)羽根切り回数および先端部の練り返し量は十分に基準を満たしたものとする。 ■品質管理 柱状地盤改良の品質管理は、改良体が設計で要求された性能を有しているかモールドコア供試体による一軸圧縮試験を実施する。 ■地盤改良系保有機械 | |
| 用途 | メーカー | 形 式 | 台数 |
| 柱状改良 | ㈱ワイビーエム | GI-50C | 2 |
| 地盤調査 | 日東精工㈱ | ジオカルテⅡ(スウェーデン式サウンディング機) | 1 |

|
株式会社山梨重機 〒403-0032 山梨県富士吉田市上吉田東1-7-19 TEL0555-22-2630 FAX0555-23-8019 |
yamajyu@yamajyu.jp |